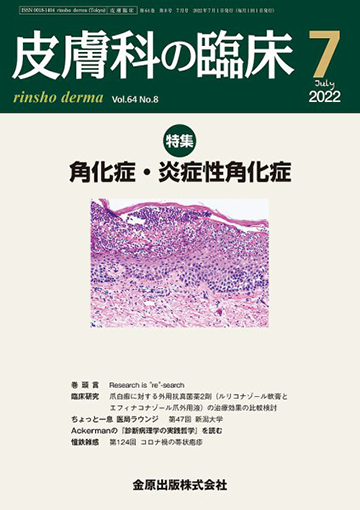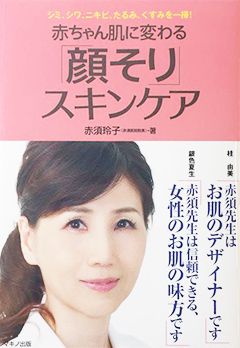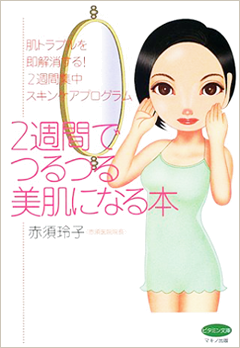雑誌・書籍
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第29回目。「有益な病理報告書の構成」というタイトルで、皮膚科医が病理医に求めるものは、臨床皮膚科学の用語で記載された正確で具体的な特異診断である。「chronic nonspecific dermatitis」や「atypical melanocytic hyperplasia」を例に挙げ、これらは病理医が正確に診断できない言い逃れであると記しています。また、どうしても診断を決定できない場合には、コメント欄に考えられる鑑別診断を記載すべきだとも言っています。
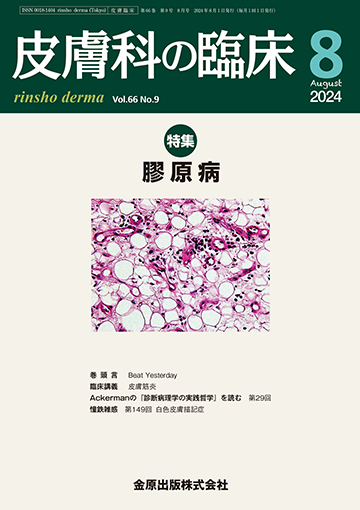
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第28回目。「誤診を最小限に食い止める」というタイトルで、病理医から臨床医に正確な病理診断が届かない原因について、いくつかの理由を挙げています。たとえば、病理所見に理解しやすい用語を使っていないとか、集中力が欠如していると適切な診断に導けないなど。診断に苦慮したときは、翌日頭がクリアになった状態で再度顕微鏡を見ると全く違った考えが浮かぶものだと記されています。
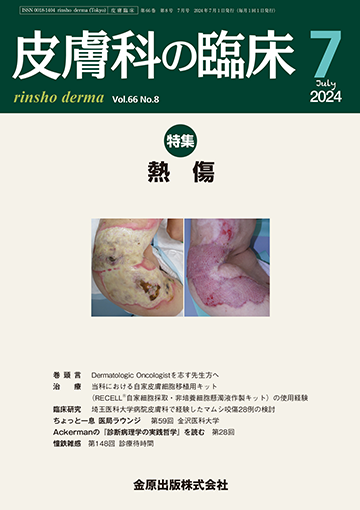
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第27回目。「HE染色が最高の特殊染色」と記されています。免疫蛍光法、酵素抗体法、電顕などを取り上げ、その歴史的意義と限界が論じられています。登場したばかりの頃は随分ともてはやされますが、一時的なブームに終わり、どれも診断確定において重要な役割を果たしてこなかった歴史が綴られています。今は遺伝子変異や染色体異常が診断の決定的意義を持つとされていますが、慎重にみたほうがよいのかもしれません。
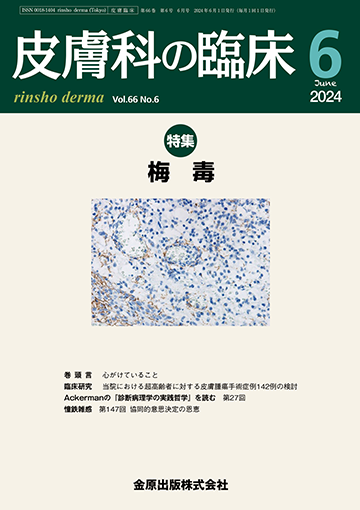
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第26回目。この回では、「生検」につい述べられています。生検に適する時期はあまりに早期であっても晩期であってもよくない。発疹は潰瘍部では得られる所見が乏しい。また、どこまでの深さを採るかは大事で、通常シェーブは避けなければならない。特に腫瘍系はしっかり脂肪組織まで摂る必要がある。ただし、乾癬や脂漏性皮膚炎、PRP、ILVEN、AK、表在性真菌症などは例外でシェーブであっても診断が付くことを説明しています。
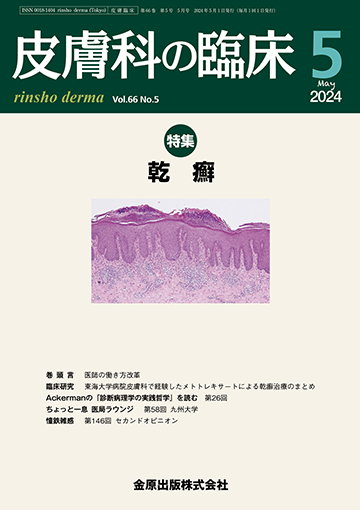
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第25回目。Ackermanの提唱するUnifying concept(統合概念)とは、一見、異なる病理所見を呈していても、基本的に同一疾患をみなされるものは、一つの疾患概念のもとにまとめるという考え方です。たとえば、ケラトアカントーマや疣状癌、増殖性外毛根鞘嚢腫がいずれもSCCの亜型や表現型とみなされるなどを例に挙げています。それによって、疾患の分類はより合理的になっていくわけです。
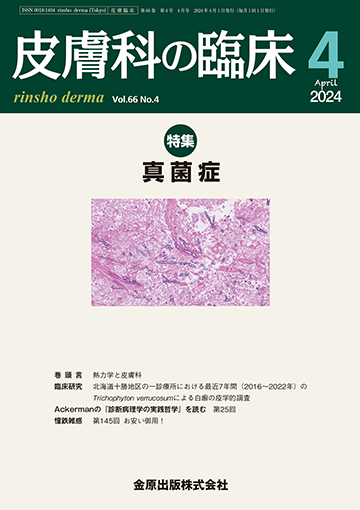
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第24回目。病理所見を読む際、どこが重要所見なのか、特異的所見が存在するかどうかがポイントとなります。それはしばしば最弱拡大によってなされ、良、悪性腫瘍の鑑別には個々の細胞の形態よりも全体構築が重要であることが記されています。この章では、他に、メラノーマの診断基準が長年にわたって明記されてこなかった歴史が述べられており、Ackermanによって初めて診断基準が確立された経緯も示されています。
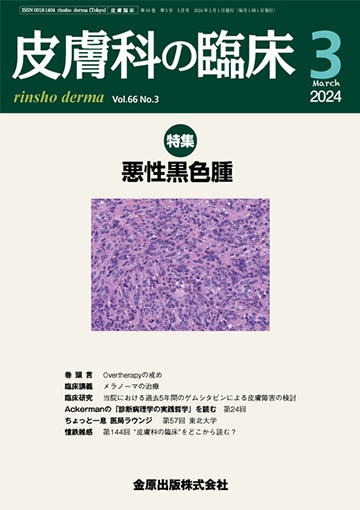
「金原出版:皮膚科の臨床(2024年02月号)ウイルス感染症」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第23回目。特定の病理組織所見には、臨床的な意義があることを解説しています。たとえば、真皮内の線維化やメラノファージの存在、形質細胞の浸潤、細胞の壊死像など、メラノーマ原発巣の完全消褪所見から予後を推測できることなどが例に挙げられています。しかし、必ずしも消褪所見が予後良好をあらわす所見でないことも書かれており衝撃的でした。
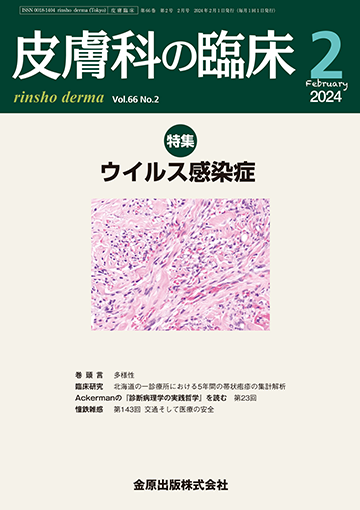
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第22回目。鑑別診断とは,臨床的あるいは病理組織学的に類似の所見を呈する疾患を判別する作業のことであり、この臨床的鑑別診断が病理組織診断の確定に役立つことがあることを解説しています。それは,臨床医が常に一定の誤診を犯す疾患が存在するからであり、臨床的にほぼ常に決まった誤診をされる疾患については,その臨床診断名が病理組織診断の確定に大きな手助けとなる、と述べています。
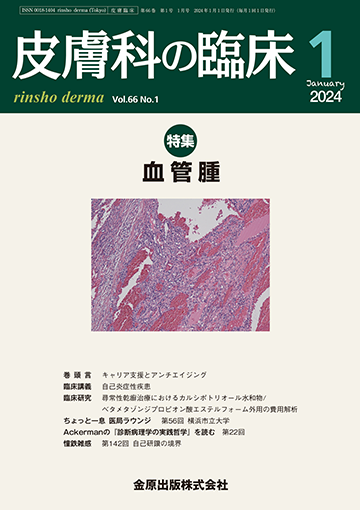
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第21回目。Cliches(クリシェイ;常套句)とは、owl eye nucleiやCommas and tadpolesのように、古くからLeverの教科書に載っているような決まり文句でありますが、Ackermanはこれらを、言い古された新味のない陳腐な表現だと否定しています。なぜなら、これらの所見は特定の疾患に特異的に見られる所見でない上に、生き生きと深く考察しようとする学習態度には何の役にも立たない、と述べています。
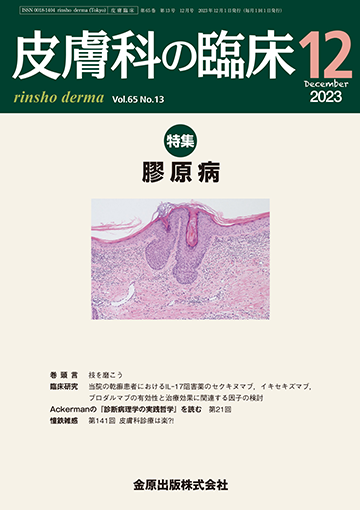
「金原出版:皮膚科の臨床(2023年11月号)日常診療に潜むリンパ腫・リンパ増殖性疾患」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第20回目。古くから正しいと信じられてきたことの中には誤りがあって、これをAckermanは「神話mythology」と称しています。たとえば、小型の類乾癬とT細胞リンパ腫とが無関係とされていることや、ケラトアカントーマが良性疾患であること、脂腺母斑から基底細胞癌が多く発生するなど、これらは真実でないので惑わされないようにと述べています。
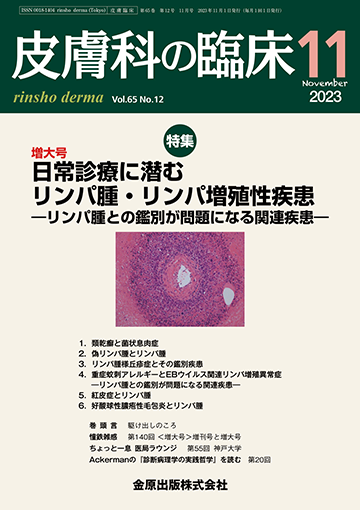
「金原出版:皮膚科の臨床(2023年10月号)生活習慣が関連する皮膚疾患」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第19回目。皮膚病理学の診断基準には例外があり、それを習得することが誤診を回避する意味でとても重要であることを解説しています。たとえばKamino小体がメラノーマでも検出されることなど。また、同一疾患でも発生場所や患者年齢、人種によっても診断基準に差異が生じることも知識として知っておかなければならないと述べています。
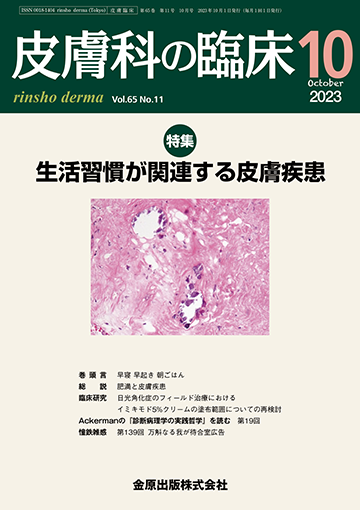
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第18回目。診断の落とし穴について、Spitz 母斑とメラノーマ、黄色肉芽腫と肉腫を例に挙げながら解説しています。また、一度の失敗(落とし穴にはまること)は仕方のないものの、その理由を知識として記憶し二度と同じ失敗をしないように学ぶことも大事だと説いています。
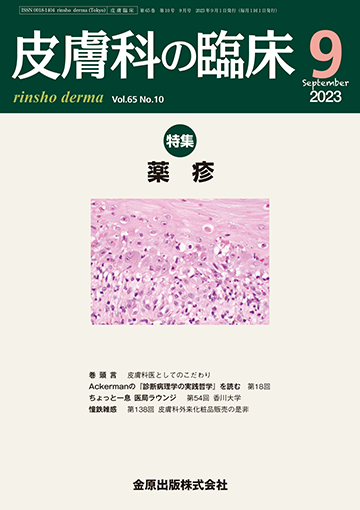
シミ、しわ、たるみと遠ざける60代、70代からやるべき「洗顔、保湿、紫外線ケア」など、正しいスキンケアの基本を紹介しました。正しいスキンケアの第1歩は、自分の肌質をまず知ることです。
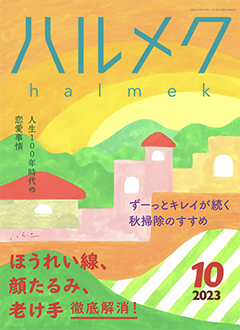
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第17回目。鑑別診断のリストが長いほど知識が豊富な医師であるという考えにとらわれて、むやみにたくさん鑑別診断をあげるべきではない。理想的には、鑑別診断のリストが短くて唯一の正しい診断のみをあげることができる病理医こそが真に有能であることを解説しています。
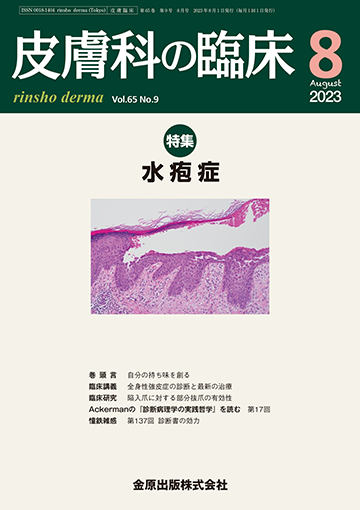
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第16回目。病理組織所見が酷似していて、鑑別が難しい疾患について例を挙げながら解説しています。そして、類似の組織所見を呈するけれども、臨床情報や検査所見を詳細に検討すれば鑑別できる疾患と、ほぼ同等の組織所見を呈しHE 標本では鑑別が不可能な疾患があることも疾患を挙げながら記しています。
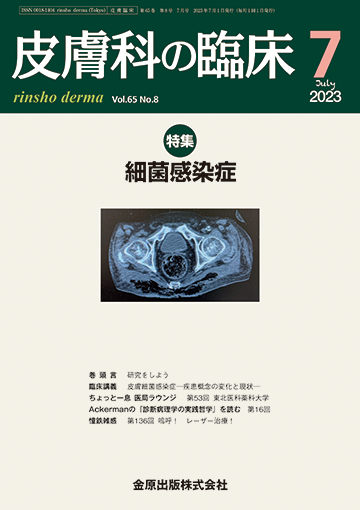
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第15回目。パターン分析に基づく皮膚病理組織のアルゴリズム的診断法の有用性について、具体例を挙げながら説明しています。これまで一貫した診断手順が存在しなかった歴史の中で、誰でも使う事のできる汎用的診断手順の創案は高く評価されました。また、臨床情報なしでも組織標本から診断に有用なヒントが得られることも記されています。
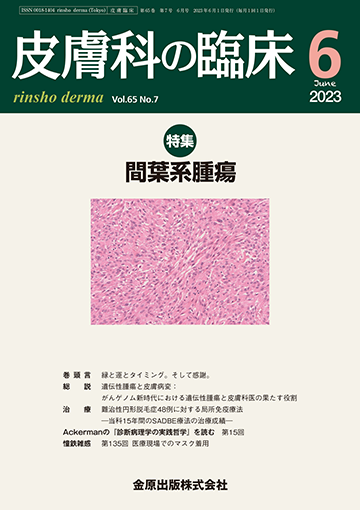
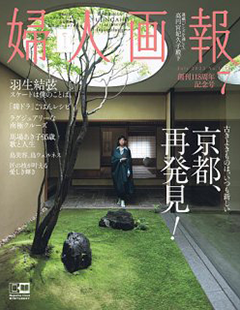
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第14回目。皮膚病理組織診断において、最弱拡所見は最も重要であり強拡大所見は誤診を犯す危険性が高まることを警告しています。弱拡大での組織構造の変化と細胞浸潤のパターン分析は炎症から腫瘍,過形成,過誤腫,形成異常,囊腫,沈着症まであらゆる種類の皮膚疾患に適用することができることが書かれています。

Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第13回目。「診断の手掛かり」所見は、診断確定の必須条件ではないがヒントになるものを指しますが、例としてSpitz母斑のKamino小体や、LE profundusのムチン沈着、メラノーマのsolar elastosisが挙げられています。それ以外に、300項目のヒントをまとめた書籍が紹介されています。
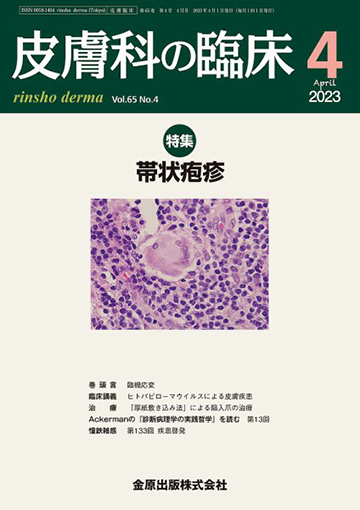
「金原出版:皮膚科の臨床(2023年03月号)悪性上皮系腫瘍」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第12回目。「錯覚と現実」というテーマで書かれています。皮膚病理組織診断における錯覚(誤診)を防止するには,診断の落とし穴や診断の手掛かり所見をなるべく多数知っておく必要があり、また過去に経験した類似の誤診症例を思い起こすことも役に立つことが記載されています。
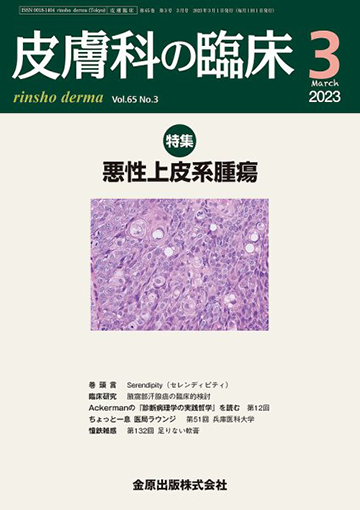
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第11回目。病理診断という形態学的判断は100%主観的なものであるため、研究者が合意した確かな診断基準が存在しなければ,首尾一貫した確実な診断を行うことができないことを説いています。また、用語の定義や、再現性のある正確で信頼に足る診断基準は、症例の積み重ねで新たな事実が明らかになれば改訂、改良する必要がある事も記されています。
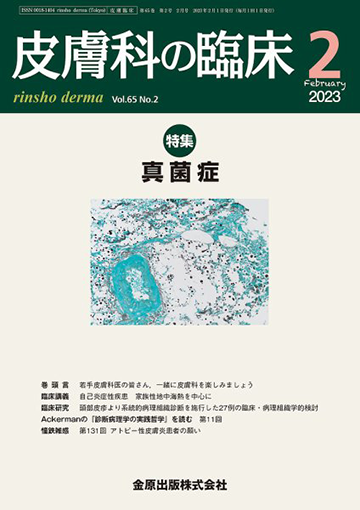
「金原出版:皮膚科の臨床(2023年01月号)免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象(irAE)」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第10回目。一つの疾患が多彩な現れ方をするというテーマで、たとえば、類乾癬に分類されている種々の皮膚疾患は本質的には菌状息肉症であること(これには異論もありますが)や、BCC も臨床・組織学的に多数の病型があり、年齢が進むと二次性腫瘍として生じてくることもある。そういう点も含めて多彩な現れ方を示すことを知っておかなければならないことを説いています。
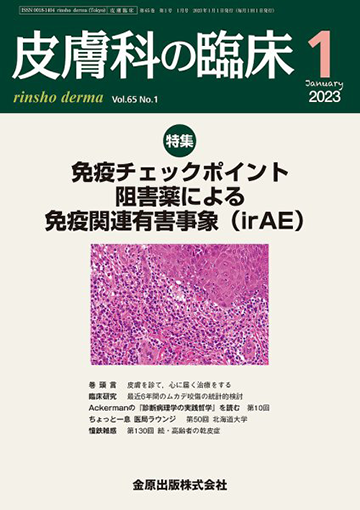
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第9回目。病変の一生(時間的推移)というテーマで、各疾患は初期,最盛期,晩期という時間的な推移を示し,それを構成する個々の皮疹も経過とともに変化する。人間が新生児から老人まで時とともに変わっていくように,病変も経過によって大きく変化するので、病理医は病変の時間的推移の全行程を頭に入れておかなければならないと書かれています。
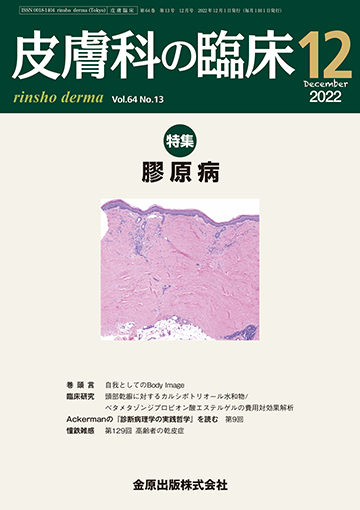
「金原出版:皮膚科の臨床(2022年11月増大号)皮膚科領域における細菌・抗酸菌感染症の最新トピックス」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第8回目。皮膚科医は皮膚病理学に重きを置いたうえで,一般病理学の基礎も修める必要がある。それは皮膚科学が他の臓器にも病変をきたす全身疾患を取り扱うだからである。ただし、両者を完璧に履修しようと思うとどちらも中途半端に終わってしまうので、あくまでも皮膚病理に重点をおくべきであると書かれています。
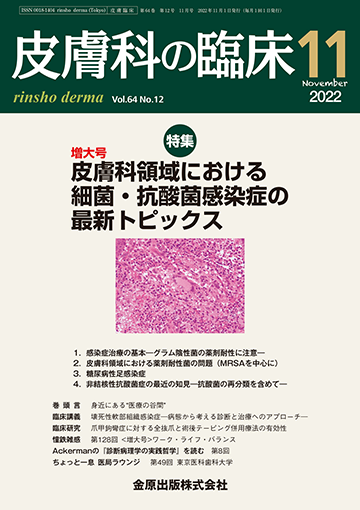
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第7回目。皮膚科医は皮膚病理組織学を理解することによってはじめて,どうしてそのような臨床所見を呈するのかを理解することができる。皮膚科学の熟達には皮膚病理組織学の知識が欠かせないことが書かれています。
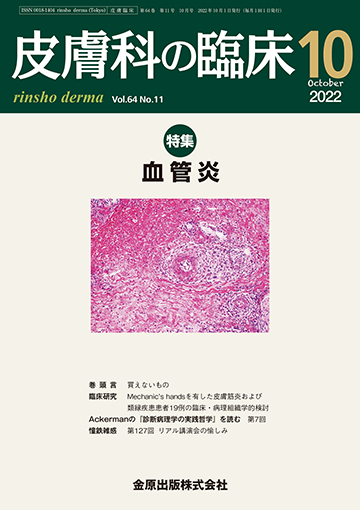
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第6回目。皮膚病理組織学の修得には臨床皮膚科学の知識は不可欠です。皮膚科医は臨床所見から病理組織像を想像することで臨床の認識能力を養うことができると書かれています。
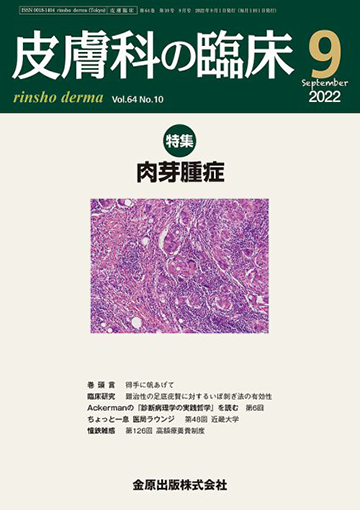
「まつげ・顔のうぶ毛・眉毛の正しい扱い方を知ろう!『顔のうぶ毛』編」
「毛を制するものが、顔印象を制す!」という内容で顔のうぶ毛の剃り方を解説しました。

「金原出版:皮膚科の臨床(2022年08月号)蕁麻疹・痒疹」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第5回目。言葉を正確に使うことができなければ(病理用語が正しく定義されていなければ)、思考の正確さは得られない(病理学者同志の言葉に混乱が生じて意思伝達がうまくいかなくなる)。
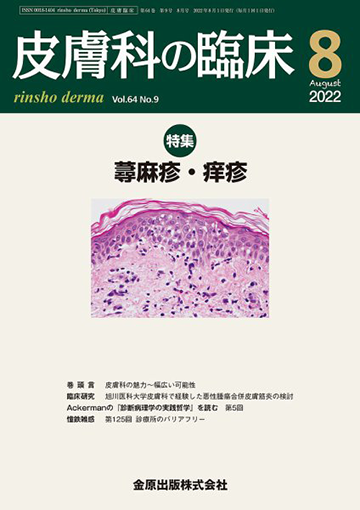
「金原出版:皮膚科の臨床(2022年07月号)角化症・炎症性角化症」
Ackermanの著書『A Philosophy of Practice of Surgical Pathology:Dermatopathology as Model(皮膚病理学を範型とする診断病理学の実践哲学)』の内容を斎田俊明先生との対談によって進めていく第4回目。組織を読む時の心得:「Open Mind, Accurate Observation, Profound Knowledge, Critical Thinking,Reasonable Interpretation」について解説されています。